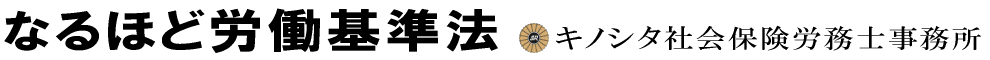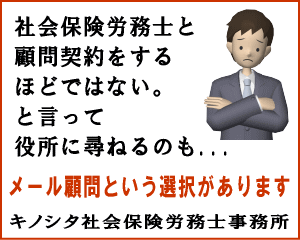有給休暇の出勤率の計算【八千代交通事件】
なるほど労働基準法 > 有給休暇 > 有給休暇の出勤率の計算
八千代交通事件 事件の概要
会社が従業員を解雇したのですが、従業員は、解雇は無効であると主張して会社を提訴しました。それから約2年後に、裁判によって、解雇は無効であると認められて、従業員は職場に復帰することになりました。
職場に復帰した後、従業員が5日間の年次有給休暇を請求して、会社を休みました。
会社は、労働基準法第39条第2項で規定されている年次有給休暇の成立要件を満たしていないと判断して、従業員が休んだ5日間は欠勤扱いとして、5日分の賃金を支払いませんでした。
これに対して従業員が、年次有給休暇の請求権があると主張して、賃金の支払いを求めて会社を提訴しました。
八千代交通事件 判決の概要
労働基準法第39条第2項で定められている前年度の出勤率が8割以上という年次有給休暇の請求権の成立要件は、労働基準法が制定された当時の状況等を踏まえて、自己都合による欠勤が多い従業員を対象外とする趣旨で定められたものである。
このような趣旨に照らすと、前年度の暦日において、就業規則等で定められた所定労働日のうち、従業員の都合によるとは言えない不就労日については、会社の経営上の障害による休業日や不可抗力など、その事情を考慮して出勤日数に算入するのが相当でない場合は別として、出勤率を算定する際は全労働日に含めた上で出勤日数に算入するべきである。
解雇が無効と判断された場合など、正当な理由がないにもかかわらず、従業員が会社から就労を拒否されて就労できなかった日は、従業員の都合によるとは言えない不就労日である。
このような日は会社の都合による不就労日であっても、その事情を考慮すると出勤日数に算入するのが相当である。労働基準法第39条第1項及び第2項の出勤率を算定する際は、全労働日に含めた上で出勤日数に算入するべきである。
これを本件について見ると、従業員は会社による無効な解雇によって、正当な理由がないにもかかわらず、就労を拒否されて就労できなかったのであるから、その期間は労働基準法第39条第2項の前年度の出勤率を算定する際は、全労働日に含めた上で、その全部を出勤日数に算入するべきである。
したがって、従業員は、所定の年次有給休暇の請求権の成立要件を満たしている。
解説-有給休暇の出勤率の計算
年次有給休暇の請求権の成立要件を満たしているかどうかが争われた裁判例です。
裁判で解雇が無効と判断されて、職場に復帰するまで、約2年間の不就労の期間がありました。年次有給休暇の成立要件である前年度の出勤率を計算する際に、この約2年間の不就労期間を、
- 全労働日から除外するのか
- 全労働日に含めるのか(その上で出勤日数に算入する)
が争点になりました。全労働日から除外すると、分母(全労働日)がゼロになって、年次有給休暇の成立要件を満たしませんので、請求権は生じません。会社の主張はこちらです。
全労働日に含める(その上で出勤日数に算入する)と、出勤率が100%となって、年次有給休暇の成立要件を満たしますので、請求権が生じます。従業員の主張はこちらです。
なお、次の期間については、労働基準法(第39条第10項)によって、出勤したものとみなす(全労働日に含める)ことが定められています。
- 業務上の傷病による休業期間
- 育児休業又は介護休業の期間
- 産前産後の休業期間
- 年次有給休暇を取得した期間
これらの休業については、従業員に不利益が及んで取得をためらわないようにという配慮がされています。
また、次の日(期間)については、通達によって、出勤率を計算する際は、分母となる全労働日から除外することが示されています。
- 不可抗力による休業日
- 会社の経営上の障害による休業日
- 正当なストライキや争議行為による不就労日
実は、この判決が出る前に、次のような通達(要約)がありました。
「懲戒解雇の日より解雇の取消しの日までの間は会社の責に帰すべき理由により労働できなかったものと解すれば、解雇の取消しにより復帰した従業員についての労働基準法第39条第1項の全労働日の算定にあたっては、1年の総日数から就業規則により定められている年間の休日数の外、懲戒解雇の申し渡しにより労働できなかった日数を差引き計算すべきである。
労働日が零となる場合は、前年に労働日のあることを前提とする労働基準法第39条の解釈上8割以上出勤するという法定要件を満たさないから、年次有給休暇の請求権は発生しない。」
無効な解雇によって出勤できなかった日数は全労働日から差し引いて、前年度の労働日がゼロになる場合は年次有給休暇の請求権が発生しないことが示されていました。つまり、会社の対応は通達に準拠したものでした。
しかし、最高裁判所の判決はこれとは正反対で、会社が行った解雇は不当なもので、それが原因で、従業員に年次有給休暇が付与されないという不利益が及ぶことは適当ではない、従業員に不利益が及ばないように、出勤率を計算する際は、無効な解雇によって出勤できなかった日数は全労働日に含めた上で、その全部を出勤日数に算入するべきであると判断しました。
最高裁の判断が正しいとすると、通達が間違っていたことになります。なお、通達とは、行政機関が統一的な対応をするためにその職員に通知をする文書のことで、事務の処理や法律の解釈等を示したものです。最高裁判所で、このような判決が出たことを受けて、通達が書き換えられました。
従業員の都合によるとは言えない不就労日は、上の1.から3.までのケースを除いて、全労働日に含めた上で出勤日数に算入することが示されて、その上で次の内容が追加されています。
「例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、従業員が会社から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。」
今後は、「従業員の都合によるとは言えない不就労日」については、出勤率を計算する際は、出勤日とみなす必要があります。