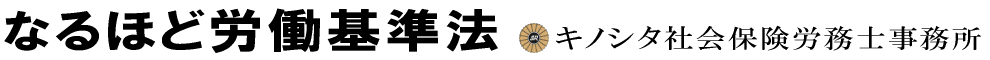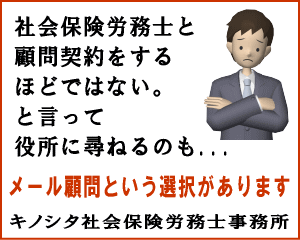労働時間の適用除外【日本マクドナルド事件】
日本マクドナルド事件 事件の概要
飲食店のチェーン店を運営する会社の就業規則では、店長以上の従業員を管理監督者と位置付けて、割増賃金を支払っていませんでした。
これに対して店長が、労働基準法上の管理監督者に該当しないと主張して、過去2年分の割増賃金の支払いを求めて、会社を提訴しました。
日本マクドナルド事件 判決の概要
店長は、店舗の責任者として、アルバイトの採用や育成、従業員の勤務シフトの決定、販売促進活動の企画・実施等に関する権限を行使し、会社の営業方針や営業戦略に即した店舗運営を遂行するべき立場にあるから、店舗運営において重要な職責を負っていることは明らかである。
しかし、店長の職務及び権限は店舗内の事項に限られ、経営者と一体的な立場で、労働基準法の労働時間等の枠を超えて活動するような重要な職務と権限が付与されているとは認められない。
店長は、従業員の勤務シフトを決定する際、自身の勤務スケジュールも決定するが、店舗では、各営業時間帯にシフトマネージャーを置くことになっているので、シフトマネージャーを確保できない営業時間帯は、店長が自らシフトマネージャーを務めることになる。
そのため、7月は30日以上、11月から翌年1月にかけては60日以上の連続勤務を余儀なくされ、2月から5月にも早朝・深夜の営業時間帯のシフトマネージャーを多数回務めなければならなかった。その結果、時間外労働が100時間を超える月もあるなど、労働時間は相当長時間に及んでいた。
店長は、自らのスケジュールを決定する権限があり、早退や遅刻に関して上司の許可を得る必要はなく、形式的には労働時間の裁量がある。
しかし、実際には、店長としての業務を遂行するだけで相応の時間が必要で、自らシフトマネージャーとして勤務することにより、法定労働時間を超える長時間の時間外労働をせざるを得ない。このような勤務実態からすると、労働時間の裁量があったとは認められない。
会社は、店長が行う労務管理、店舗の衛生管理、商圏の分析、近隣の商店街との折衝、店長会議の参加等の職務は、労働基準法による労働時間の規制になじまないと主張する。
しかし、店長は、会社の事業全体を経営者と一体的な立場で遂行する立場にはなく、会社から提供された営業方針、営業戦略、マニュアルに基づき、店舗の責任者として、店舗従業員の労務管理や店舗運営を行う立場にとどまるもので、そのような立場の店長が行う職務は、労働時間の規制になじまないとは言えない。
また、店長の平均年収は約710万円、アシスタントマネージャーの平均年収は約590万円(割増賃金を含む)で、管理監督者として扱われている店長と管理監督者として扱われていないアシスタントマネージャーの収入には、相応の差異が設けられているように見える。
しかし、S評価の店長の年収は約780万円、A評価の店長の年収は約700万円、B評価の店長の年収は約640万円、C評価の店長の年収は約580万円で、店長全体の10%を占めるC評価の店長の年収は、アシスタントマネージャーの平均年収より低額である。
また、店長全体の40%を占めるB評価の店長の年収は、アシスタントマネージャーの平均年収を上回るが、その差額は年額で約40万円にとどまっている。
そして、店長の週40時間を超える労働時間は月平均39.3時間で、アシスタントマネージャーの月平均38.7時間を超えているが、店長の勤務実態を考慮すると、店長の賃金は、労働基準法の労働時間の規定の適用が除外される管理監督者に対する待遇としては十分とは言い難い。
また、会社では、各種インセンティブを設けているが、これは業績の達成を条件として支給するもので、店長だけではなく、他の従業員も支給対象としている。インセンティブを設けていることは、店長を管理監督者として扱い、労働基準法の労働時間等の規定の適用を除外することの代償措置として重視することはできない。
以上により、店長は、その職務内容、権限及び責任の観点からしても、その待遇の観点からしても、管理監督者に当たる者とは認められない。したがって、店長に対して、時間外労働及び休日労働に対する割増賃金を支払わなければならない。
解説-労働時間の適用除外
全国展開をする飲食店のチェーン店の店長について、労働基準法上の管理監督者に該当するかどうか争われた裁判例です。
労働基準法(第37条)によって、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)を超えて労働した時間に対して、割増賃金を支払うことが義務付けられています。
これが原則ですが、労働基準法(第41条)によって、”管理監督者”に該当する場合は、法定労働時間の規定が適用されません。その結果、割増賃金の支払い義務が免除されます。
企業としては、管理監督者の範囲を拡げて、割増賃金の支払いを抑制したいと考えますが、「管理職=管理監督者」は必ずしも成立しません。「名ばかり管理職」と呼ばれて社会問題になっています。
管理監督者と認められるためには、経営者と一体的な立場で、労働時間の規制の枠を超えて活動する者であることが前提となります。具体的な条件として、重要な職務及び権限が与えられていて、賃金等の待遇がそれなりに優遇されている必要があります。
一律に、部長や課長といった役職で決まるのではなく、個々の事案ごとに、その従業員の職務及び権限の範囲、労働時間の裁量性、賃金等の優遇措置等を考慮して判断することになります。
一般的に、チェーン店の店長については、アルバイトの採用や育成、勤務シフトの決定等の権限が与えられて、店舗運営について重要な職責を負っているとしても、その権限は店舗内の事項に限られます。
この裁判でも、経営者と一体的な立場で、企業全体の経営方針を決定するような重要な職務や権限が付与されていない、労働時間については実際には裁量がない、賃金は管理監督者の待遇として十分ではないとして、労働基準法(第41条)の管理監督者には該当しないと判断しました。
管理監督者の取扱いが否定されると、会社にとっては大きなリスクです。仮に、1時間当たりの賃金が1,600円、時間外労働の時間が毎週10時間、年50週とすると、割増賃金は1年間で100万円(=1,600円×1.25×10時間/週×50週)になります。
なお、以前は労働基準法上、賃金の請求権の時効は2年でしたが、民法の改正に伴って、賃金の請求権の時効が3年に延長されました。前提条件を低く設定していますが、それでも3年で300万円になります。