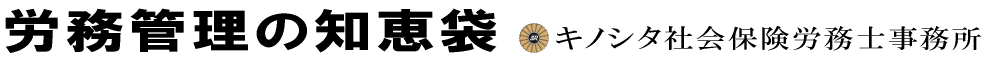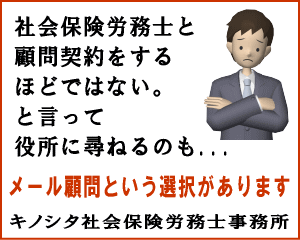労働契約法とは
労働契約法とは
労働条件(労働時間や休日、賃金など)の最低基準を定めた法律として労働基準法がありますが、最近は、解雇や賃下げというような労働基準法では対応できないトラブルが増えています。
このようなトラブルは最終的には裁判で決着するのですが、過去の裁判例の積み重ねによって、例えば、解雇が有効か無効かを判断するルール(「判例法理」と言います)が確立されているものがあります。
そして、裁判ではこの判例法理に当てはめて判断するのが一般的です。しかし、このような判例法理は、一般の従業員や企業経営者には余り知られていません。
そこで、判例法理を法律として整理し明らかにすることによって、労使間のトラブルを未然に防止することが期待されます。このような背景から「労働契約法」が制定されました。
なお、労働契約(法)は労使の個別の合意を原則としている性質上、労働基準法のような罰則はなく、労働基準監督署による指導等もありません。
しかし、法律として根拠が示されたことになりますので、従業員側から見ると法律違反を指摘しやすくなります。つまり、企業としては今まで以上に慎重な対応が求められます。
では、労働契約法には、どういうことが定められているのか見てみましょう。
労働契約の内容の理解の促進
会社が従業員に提示する労働条件や労働契約の内容については、できるだけ書面で確認し、従業員の理解を深めるようにしないといけません。
安全配慮義務
会社は従業員の生命や身体、心身の健康などの安全が確保されるよう配慮しないといけません。
従業員は普通、会社の指定した場所で、会社の用意した設備や器具を用いて、会社の指示によって業務を行うことから、判例においても、会社には従業員の安全を確保するよう配慮する義務があるとされています。
例えば、安全装置を設けるべき機械に安全装置を設けなかったり、安全教育が不十分だったり、過重労働を強要したりして、事故や病気になったときは損害賠償を請求されることになります。
労働契約の成立
労働契約を結ぶときに、労働契約として定めていなかった部分については、就業規則で定めている内容が適用されます。ただし、その就業規則が合理的な内容で、従業員に周知させている場合に限ります。
なお、従業員から見て、就業規則より有利な条件で労働契約を結んだときは、その(従業員にとって有利な)労働契約が優先されます。
労働契約の内容の変更
会社と従業員が合意すれば、労働契約の内容を変更することができます。
就業規則の変更による労働契約の変更
会社が一方的に就業規則を変更しても、従業員の合意が得られないときは、その就業規則は適用されません。
つまり、会社が一方的に就業規則を従業員にとって不利益に変更することはできないということです。
就業規則の変更ができる例外
原則的には前の項目のとおりですが、例外的に次の要素を総合的に考慮して就業規則の変更が合理的である場合は、就業規則を不利益に変更することが認められます。
- 従業員の受ける不利益の程度
- 変更の必要性の内容・程度
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合や従業員代表等との交渉の経緯
- 代償措置(他の労働条件の改善状況)
- 他の(不利益にならない)従業員の対応
- 世間一般の状況
なお、就業規則を変更しても変更されることはない、と個別に合意していた部分(就業規則より従業員にとって有利に定めていた部分)については、その労働契約(合意)が優先されます。
出向
会社による出向命令が、権利を濫用したものと認められる場合は無効になります。
権利の濫用に当たるかどうかは、出向を命じる必要性の有無、従業員の選定が適切かどうか等の事情を考慮して判断されます。
この出向は在籍出向のことで、転籍出向(籍も移される出向)は含まれていません。
懲戒
会社による懲戒処分が、権利を濫用したものと認められる場合は無効になります。
権利の濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因となった従業員の行為の性質や程度などの事情を考慮して判断されます。
解雇
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効となります。
この規定は労働基準法で定められていましたが、労働契約法に移動されました。
期間の定めのある労働契約
期間の定めのある労働契約をしたときは、やむを得ない理由がない限り、その契約期間が満了するまで会社は従業員を解雇できません。
また、期間の定めのある労働契約について、必要以上に短い期間を定めて、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しないといけません。
なお、「必要以上に短い期間」は個別のケースに応じて判断されるものとして、特定の期間は明らかにされていません。
(2010/3更新)
(2014/5更新)

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。