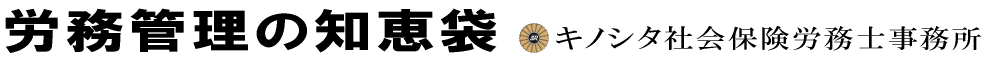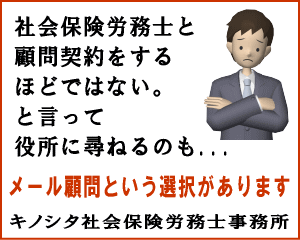労働審判とは
労働審判とは
解雇や賃金(割増賃金)の不払など、労使間のトラブルが増加しています。
2001年からあっせん制度が始まりましたが、あっせんには強制力がないため、労使関係がこじれると役に立たないという欠陥がありました。
労働審判制度は、こうした背景を踏まえて、裁判所で迅速・適正かつ実効的に労働紛争を解決する制度として2006年4月からスタートしました。
労働審判の特徴
3回以内の審理で決着
労働審判は、原則3回以内の審理で終了します。
最初に申立書が提出されると、1回目の期日が指定され、相手方はその期日までに答弁書を提出します。
そして、1回目で争点や証拠の整理が行われ、2回目で補充や証拠調べが行われ基本的に主張立証が終了します。この間に調停による解決の見込みがあれば、調停が試みられます。
次の3回目は調停へ向けた当事者への説得作業が中心となり、調停が成立しなかった場合は「労働審判」(通常訴訟の判決)が出されます。
最初の申立書と答弁書は書面で提出されますが、3回の審理で決着するため、その後は原則として口頭でやり取りすることになっています。
裁判上の和解と同じ効力が発生
審理の途中で調停が成立するか、労働審判が出て2週間以内に異議を申し立てないと、労働審判が確定します。労働審判が確定すると、裁判上の和解と同じ効力(強制執行が可能)が発生します。
労働審判は、あっせんと違って実効性のある解決が図られます。
異議のある場合は訴訟に移行
労働審判に対して異議が申し立てられると、労働審判は無効になって自動的に通常の訴訟に移行します。
訴訟になってもある程度の結論が予想できますので、労働審判の段階で解決されることが多くなると思います。
柔軟な審判が可能
裁判での判決は、白か黒かの判断しかありません。
例えば、不当な解雇に関して、従業員が「本当は復職ではなく、解決金をもらいたい」と思っていても、裁判ではその意向に沿った判決は得られません。あくまでも解雇が無効か有効かの判断が行われます。
このような場合は、会社も復職より金銭の支払いを望むケースが多いと思いますので、労働審判では金銭の支払を命じる審判が出されるでしょう。このように当事者の実情に応じた審判によって、訴訟よりも柔軟な解決が図られます。
出頭義務あり
あっせんでは、相手方が出頭しないと何も進まないという問題がありましたが、労働審判では出頭が強制され、拒否した場合は罰金が科されます。
非公開
手続は非公開で行われます。
労使間トラブルの解決制度
次のように、労使間のトラブルについて、解決制度の選択肢が増えました。
- 【あっせん】
労使ともに積極的にトラブルを解決したいと思っていて、何か客観的な判断基準が欲しいという場合 - 【訴訟】
相手を「絶対に許さない!」という場合 - 【労働審判】
あっせんと訴訟の中間
労使間トラブルの解決の制度が増えましたが、トラブルは表面化させないで、社内で解決できれば良いのは、言うまでもありません。
経営者や管理職の方が誠実に対応していたら、問題が大きくならなかったのに、というケースがよくあります。特に、人格を否定するような発言はもってのほかです。注意しましょう。
(2008/1作成)
(2014/5更新)