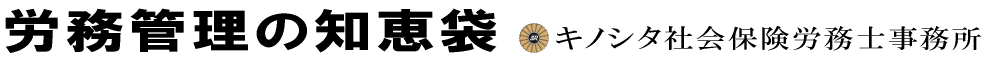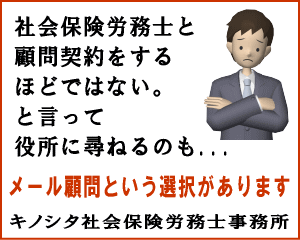従業員が逮捕されたら
従業員が逮捕されたら
従業員が逮捕されると、本人から連絡をすることができませんので、通常は弁護士や家族から会社に連絡が入ります。
令和3年の刑法犯の認知件数は約60万件、検挙件数は約30万件ですので、可能性は少なくありません。
刑事手続きの流れ
逮捕されると、次のような流れで進みます。
- 逮捕
・・・被疑者(容疑者)は警察署に留置されて、警察は48時間以内に検察へ送致するか、釈放するか判断します。 - 送致
・・・検察は24時間以内に、裁判所に勾留を請求するかどうか判断します。1.と2.の合計72時間(3日間)は、家族であっても面会は許されません。面会(接見)は弁護士のみが許されます。勾留の必要がないと判断したときは、釈放して在宅事件に切り替わる場合があります。そうなると、捜査期間(起訴又は不起訴の判断)が長引くことが予想されます。 - 勾留
・・・裁判所が勾留を決定すると、被疑者は最長で20日間勾留されます。この間に事情聴取や実況見分を行って、検察が起訴又は不起訴の判断をします。弁護士は自由に面会できますが、それ以外の者は1日1組限り、1組につき15分まで等の制限付きで面会できるようになります。ただし、裁判所が接見禁止を決定した場合は、家族でも面会はできません。 - 起訴
・・・起訴後も判決が言い渡されるまで、勾留されるのが原則ですが、保証金を納付して保釈が認められる場合があります。 - 裁判
・・・単純な事件で本人が犯罪事実を認めている場合は、起訴から約2ヶ月後に一審の判決が言い渡されるケースが一般的です。
情報収集
従業員の身柄が拘束されたときは、今後のスケジュールを把握して、業務の調整や引継ぎをする必要がありますので、次のような事項について、家族や弁護士、可能であれば本人から情報収集を行います。ただし、弁護士には守秘義務がありますので、教えてもらえない場合があります。
- 逮捕された日時
- 犯罪行為の内容及び罪名
- 勾留されている場所
- 弁護人を選任したか?
- 本人が犯罪事実を認めているか?
- 被害者と示談が成立したか?
- 起訴又は不起訴の見通し
- 釈放される見込みがあるか?
従業員の弁護をするために、会社の顧問弁護士を紹介して欲しいと依頼されることがありますが、後日に、会社が懲戒解雇等を行って、従業員と対立関係になる可能性がある場合は応じるべきではありません。弁護士は、対立関係にある双方の代理人になることが禁止されていますので、紹介に応じると、懲戒解雇等に関して、会社から顧問弁護士に相談できないようになります。
賃金の取扱い
従業員の身柄が拘束されて会社に出勤できないときは、本人の責任ですので、原則的には、欠勤扱いとして無給で処理をします。
従業員が年次有給休暇を請求したときは、有給で処理をします。また、本人が希望して、会社が認めれば、さかのぼって年次有給休暇を取得することも可能です。会社のみの判断で、年次有給休暇を取得させることはできません。
問題となるのが、従業員が釈放されて、出勤しようと思えば出勤できる状態になった場合です。従業員が出勤することによって、他の従業員が怖がったりして、業務に支障が生じる恐れがある場合は、出勤を禁止して無給で処理できると考えられます。
しかし、無給とすると、懲戒処分の出勤停止を行ったものとして、後から別の懲戒解雇を行っても無効になる恐れがあります。原則的な考え方として、1つの違反行為に対して、後から重ねて懲戒処分を行うことが禁止されています。二重処罰の禁止と言います。
したがって、出勤が望ましくない場合は、平均賃金の6割の休業手当を支払って、自宅待機を命じる方法が無難です。この場合は業務命令として行うものですので、懲戒処分には当たりません。
懲戒処分の検討
従業員が社外で犯罪行為をしても、プライベートのことですので、それだけを理由にして懲戒処分を行うことはできません。従業員の行為によって、会社の社会的な信用を失墜した場合や職場の秩序を乱した場合は、会社に悪影響が及んでいることから、制裁として懲戒処分を行うことができます。
就業規則によって、懲戒処分は譴責(始末書の提出)から懲戒解雇まで、数段階に分かれていると思いますが、犯罪行為の内容、刑罰の程度、反省の程度、業種、会社における地位や職種、前科、前歴、報道の有無、信用失墜の程度、その他の悪影響の程度等を総合的に考慮して、それに見合った懲戒処分とする必要があります。厳し過ぎる懲戒処分は無効になります。
個々の状況によりますが、1つの目安として、罰金刑の場合は懲戒解雇は認められにくい、懲役刑の場合は懲戒解雇は認められやすいです。ただし、強制わいせつ等の性犯罪については、起訴猶予になったとしても懲戒解雇は認められやすいです。迷惑防止条例違反の痴漢の場合は、ケースバイケースです。
場合によっては、犯罪行為を理由とする懲戒解雇ではなく、長期間勤務ができないことを理由にして、普通解雇を検討するケースもあります。
就業規則の懲戒事由の書き方にも注意が必要です。「有罪の判決を受けたとき」と「犯罪事実が明白なとき」では、対象範囲が異なります。結果的に不起訴になった場合は、「有罪の判決を受けたとき」を根拠にして懲戒処分を行うことはできません。ただし、「会社の信用を失墜させたとき」や「会社の秩序を乱したとき」というような規定があれば、これを根拠にして懲戒処分を行えます。
刑事裁判で起訴されると有罪率は99.9%と言われていますので、起訴された場合はその時点で、「犯罪事実が明白なとき」に該当すると考えられます。ただし、懲戒処分を行う際は、本人に弁明の機会を与える必要があります。
また、不起訴の場合は、その理由によって次の3つに分類されます。
- 嫌疑なし
・・・犯罪の疑いがないと判断された場合です。懲戒処分は不可能です。 - 嫌疑不十分
・・・犯罪の疑いがあるけれども、十分な証拠がないと判断された場合です。本人も犯罪事実を認めていなければ、懲戒処分は認められにくいです。 - 起訴猶予
・・・十分な証拠があるけれども、被害が軽微だったり、被害者と示談が成立したりして、検察の判断で起訴しない場合です。犯罪事実が明白なときに該当すると考えられます。
退職勧奨
懲戒解雇や普通解雇が認められない可能性がある場合は、退職勧奨を検討するケースもあります。本人の意思で退職届を提出すれば、退職が無効になる可能性はゼロに近いです。
勾留中に面会できる場合は、本人が署名すれば提出できるように退職届を持参したり、家族等から退職の意向が伝えられた場合は、返信用の封筒を同封して退職届を郵送することもあります。
(2024/8作成)